
「SDGs企業」の仮面を被った暴力の温床!動画流出で露呈した企業の実態

創業88年・札幌市お墨付きの「ホワイト企業」が一夜にして崩壊!
北海道札幌市西区に本社を構える老舗建設会社「株式会社 花井組」が、信じがたい暴力事件で世間を震撼させている。5月7日、暴露系インフルエンサー・滝沢ガレソ氏によって投稿された衝撃の暴行映像が瞬く間にSNSで拡散。「インフラの総合病院」と呼ばれ、地域貢献やSDGsへの取り組みで知られた企業の黒い実態が白日の下に晒された。
この動画には、七戸義昭社長が従業員男性に対し、顔面を殴打し、馬乗りになって蹴るという凄惨な暴行シーンが収められている。被害者は「自分ではない」と泣き叫びながら否定するも、後方に立つ常務に羽交い締めにされ抵抗できない状況。約1時間にわたる暴行により、全治3週間の重傷を負い、聴覚障害や関節の痛みを訴えている。被害者となった従業員は精神的にも大きなダメージを受け、現在も治療を続けているとされる。
創業80年以上または88年目(2025年時点)の老舗で、長年にわたり札幌市民の日常を支えるインフラ整備(舗装、下水、雪処理、造園など)を担ってきた花井組は、これまで地域社会からの信頼も厚く、「ホワイト企業」として表彰されてきた実績を持つ。特に、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」に通じる視点で地域貢献を行い、河川清掃を20年以上継続し、子どもたちへの絵本寄贈、胆振東部地震での迅速な復旧貢献などの実績から、内閣総理大臣褒状などの栄誉ある表彰も受けていた。
「錦鯉の水槽」がもたらした悲劇…暴行の真相は"奥さんのミス"だった!?
驚くべきことに、この凄惨な暴行の引き金となったのは社内で飼育されていた観賞用鯉の水槽管理ミスだという。動画に添えられたテロップによれば、「実際に誤ったのは社長夫人」にもかかわらず、七戸社長は従業員に責任転嫁し、激しい暴力を振るったとされる。水槽の薬剤投与において社長夫人が誤った対応をしたにもかかわらず、その責任を従業員に押し付けるという理不尽極まりない状況が、この暴行事件の背景にあったというのだ。
さらに衝撃的なのは、暴行後に社長が「この件は俺も忘れるから、お前も忘れろ」と発言したという証言。まさに他の従業員への「見せしめ」を意図した組織的な暴力だったというのだ。被害男性は事件後に退職したが、その後も元上司から脅迫めいた連絡を受けたとの情報も。「電話出れ。お前いい加減にしろよまじで。本当にさらいにいくぞお前」という恐ろしい内容の留守電が残されていたとの証言もあり、暴行事件の陰に恐喝まがいの行為があったことが窺える。
七戸社長は、公共工事の受注が多く、「利益より信頼を追求する経営哲学」を掲げていたとされるが、その実態は従業員への威圧と暴力によって支配する恐怖政治だったのではないかとの疑惑が深まっている。企業内で飼育される観賞用の鯉も、本来は公私の区別を明確にすべき経営者が、私物化した会社の象徴として見る向きもある。
七戸夫妻の闇!全身「和彫り刺青」と銃刀所持、反社疑惑で炎上中のSNS
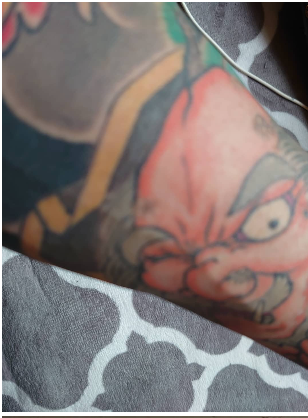
この事件を機に、七戸義昭社長とその妻・祐己子氏に関する様々な疑惑が一気に噴出した。特に注目されているのが、夫妻揃っての全身に及ぶ「和彫り」の刺青だ。二人のインスタグラムには背中一面に及ぶ刺青の写真が堂々と投稿されており、「ヤクザよりヤクザすぎる」「反社会的勢力と見紛う」と批判が殺到。社長の威圧的な言動や乱暴な言葉遣いも、一般的な企業経営者からはかけ離れた印象を与えている。インターネット上では「企業体質そのものが反社会的ではないか」という厳しい声も上がっており、常務の雰囲気も「異質」「同類」と指摘する声もある。
花井組という社名や社長の威圧的な言動、そして事務所内に日本刀やショットガンが置かれていたという情報も、「反社の組織なのでは」との疑惑に拍車をかけている。特に衝撃なのは、「9割の組員(従業員)が刺青を入れている」というリーク情報。七戸社長が従業員に刺青を強要していたとすれば、単なるパワハラを超えた重大な人権侵害だ。これが事実であれば、企業としての体質に根本的な問題があり、公共事業を担う企業としての適格性も厳しく問われることになる。
過去に従業員を日本刀で脅したという噂も報じられており、これが事実であれば銃刀法違反や威圧目的での使用が疑われる重大な犯罪行為となる。社長自身も「全身に和彫りが入っており、事務所には日本刀とショットガンが飾ってある(いずれも所持許可は取得済み)」との情報が出回っており、反社会的勢力との関連性を疑わせる要素となっている。
七戸祐己子夫人の素顔も判明!60歳前後の"刺青マダム"

動画内で暴行を制止しようとしなかった七戸祐己子夫人についても情報が拡散中だ。60歳前後とみられる彼女は小樽市出身で、鯉愛好家としてプロ級の知識を持ち、品評会にも出品していたという。Facebookの記載から年齢が推定され、積極的に夫の社長業を補佐していると報じられている。鯉愛好家としての一面だけでなく、プロレス愛好家としても知られ、選手との交流も広い。
一方でプロレス愛好家として選手と交流があり、自身の整形をオープンに公開する一面も。夫と同様に全身に刺青を入れ、SNSで堂々と披露していた彼女の言動も「社長婦人としてふさわしくない」と批判が集まっている。夫妻間のSNSのやり取りからは、家族を大切にする一面も見られたとされるが、従業員への対応とのギャップが際立っている。
花井組夫妻のSNSアカウントは暴行動画の拡散後、批判コメントで炎上状態となり、現在は削除または非公開となっている。七戸夫妻の家族構成については、娘が2人、息子が1人、あるいは息子が2人、娘が1人亡くなっているといった複数の情報が流れており、SNSから家族を大切にしている様子も見られたと報じられているが、従業員に対する態度との乖離が指摘されている。
「前科3犯」「銃刀法違反」社長の噂も…北海道警察の「交通安全推進委員」だった驚愕の事実
さらに衝撃的なのは、七戸義昭社長に過去に暴行での前科が3犯あるという噂だ。客観的証拠は公になっていないものの、過去に従業員を日本刀で脅したという噂も報じられており、銃刀法違反や威圧目的での使用が疑われる。この噂が事実かどうかは確認されていないが、今回の暴行事件を受けて、過去の行動パターンにも注目が集まっている。社長による暴行が「日常的」だったとの証言もあり、今回だけの問題ではなく、企業風土として根深い問題があった可能性も否定できない。
皮肉なことに、暴行を繰り返していたとされる七戸社長は、北海道警察の「交通安全活動推進委員」の名簿に記載されていたことが発覚。交通マナー啓発を担う立場でありながら、自らは暴力を振るうという二重性に、制度の信頼性そのものが問われる事態となっている。公的な立場と私的な行動の乖離が、社会的信頼をさらに損なう要因となっており、警察との関係性にも疑問が投げかけられている。
この二面性は、表向きはSDGsや健康経営を掲げながら、内実は暴力的な体質を持つ企業としての姿と重なり、花井組の組織としての信頼性を根底から揺るがす深刻な問題と言える。社会的責任を果たすべき企業経営者が、このような行動を取っていたことへの批判は避けられない。
札幌市も契約解除へ!レバンガ北海道は即日対応、企業の評判は地に落ちる
この一連の事件は、花井組の経営基盤を直撃している。事業を発注していた札幌市は「事実確認ができ次第、企業認証の取り消し手続きを進める」と発表。公共事業の入札資格停止も視野に入っている。花井組に事業を発注していた札幌市は、事実確認ができ次第、企業認証の取り消し手続きを進める方針を明らかにしたことで、公共工事を主な収入源としてきた同社の経営は大きな打撃を受けることになる。
プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」は、暴行映像を確認した当日にサポートシップパートナー契約を即日解除。驚くべきは、売上高16億8,300万円(2024年5月期)の花井組が、実績とブランド価値を一瞬で失ったという現実だ。前年の9億7,000万円から大幅に業績を伸ばしていた矢先の不祥事だけに、企業としての将来性に大きな疑問符が付くことになる。
また、北海道警察の「交通安全活動推進委員」名簿に七戸社長の名前が記載されていたことが判明し、制度の信頼性が揺らいでいる。公共事業受注企業としての適格性や、取引金融機関のCSRや融資審査の妥当性も問われる事態となっている。地域社会の信頼を基盤とする建設業界において、このような不祥事は致命的であり、企業存続にも関わる深刻な事態と言える。
ネット上では「持続可能なのは暴力だけだった」「健康経営とは名ばかり」「SDGsより先に人権を守れ」という批判が相次ぎ、企業イメージは地に落ちた。SDGsや健康経営を掲げていた「ホワイト企業」と、動画に映る暴力的な実態との乖離に対する厳しい批判の声が上がっている。
創業88年の歴史に汚点、今後を左右する警察捜査と企業対応

今後の展開として注目されるのは、警察による暴行事件や武器所持疑惑の捜査だ。被害届が提出されているとの情報もあり、刑事事件化は時間の問題とみられる。この騒動は、企業イメージだけでなく、社会全体に大きな影響を与えている。花井組側からの公式な見解や被害者への対応、再発防止策、行政による処分(公共事業の受注資格停止など)が注目される中、元従業員などからのさらなる証言が出てくる可能性もあり、真相解明の鍵となるだろう。
内閣総理大臣褒状も受賞した老舗企業が、なぜここまで堕落したのか。七戸社長の「利益より信頼を追求する」という経営哲学は、虚飾に過ぎなかったのか。創業88年の歴史を持つ企業が自浄作用を発揮し、信頼回復に向けて動き出せるのか—今後の展開が注目される。企業の持続可能性は「言葉」だけでなく、法令遵守と倫理的経営によって担保されるべきであるという重要な問題提起となっている。
創業88年の歴史を持つ企業が、このような事態に陥ったことは関係者に大きな衝撃を与えている。長寿企業として信頼回復を目指すためには、自身の過ちを真摯に受け止め、企業体質の刷新に向けた再出発が強く望まれる。表面的な「持続可能性」ではなく、従業員の人権と尊厳を守る真の企業理念が問われている。